-
- 板谷内科クリニックブログ
- 千葉市都賀で高血圧の数値が気になる方へ|基準・測り方・改善方法を解説
千葉市都賀で高血圧の数値が気になる方へ|基準・測り方・改善方法を解説
2025.09.16
高血圧は、血管内の圧力が持続的に正常値を上回る状態を指します。高血圧は自覚症状がほとんどないまま動脈硬化や脳卒中、心臓病などの合併症を引き起こす危険な病気です。そのため、高血圧は早期発見が極めて重要な病気です。ここでは、千葉市都賀で高血圧に不安を持つ方向けて、数値の見方、危険度、改善方法までを内科医の視点で詳しく解説します。
【目次】
千葉市都賀で高血圧の数値が気になる方へ|高血圧とは?
千葉市都賀で高血圧の数値が気になる方へ|高血圧の症状
千葉市都賀で高血圧の数値が気になる方へ|正常値と高血圧の基準とは?
千葉市都賀で高血圧の数値が気になる方へ|危険な数値はいくつから?
千葉市都賀で高血圧の数値が気になる方へ|高血圧と関連した症状
千葉市都賀で高血圧の数値が気になる方へ|正しく測るにはどうすればいい?
千葉市都賀で高血圧の数値が気になる方へ|血圧の数値を下げる方法
まとめ|高血圧の数値は千葉市都賀の内科で相談できます
千葉市都賀で高血圧の数値が気になる方へ|高血圧とは?
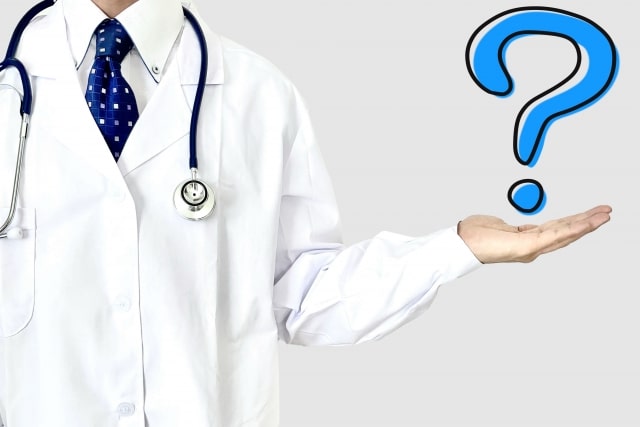
高血圧とは、血管内を流れる血液が血管壁に与える圧力が持続的に高い状態を指します。一般的に、収縮期血圧が140mmHg以上、または拡張期血圧が90mmHg以上の場合に高血圧と診断されます。高血圧の多くは本態性高血圧と呼ばれ、明確な原因が特定できないものですが、遺伝的要因、塩分の過剰摂取、肥満、運動不足、ストレス、喫煙、過度の飲酒などが発症に関与しています。
一方、腎臓病やホルモン異常などの基礎疾患が原因となる二次性高血圧も存在します。高血圧は初期段階では自覚症状がほとんどありませんが、放置すると心筋梗塞、脳卒中、腎不全などの重篤な合併症を引き起こすリスクが高まります。そのため、定期的な血圧測定による早期発見と適切な治療が極めて重要です。
千葉市都賀で高血圧の数値が気になる方へ|高血圧の症状

高血圧は「サイレントキラー」と呼ばれるように、初期段階では自覚症状がほとんど現れません。しかし、血圧が著しく高くなったり、長期間持続したりすると、様々な症状が現れることがあります。ここでは、高血圧に関連する症状について解説します。ただし、これらの症状があるからといって必ずしも高血圧とは限らず、他の疾患が原因の場合もあることを理解しておくことが重要です。
頭痛
高血圧に伴う頭痛は、特に後頭部や首の付け根付近に現れることが多く、朝起きた時に強く感じる傾向があります。この頭痛は血圧上昇による血管の変化などが関与して生じ、重苦しい感じや締め付けられるような痛みが特徴的です。高血圧に伴う頭痛は、通常の頭痛薬では改善しにくく、血圧が正常化すると軽減することが多いです。しかし、突然激しい頭痛が現れた場合は、高血圧性脳症や脳血管障害の可能性もあるため、速やかに医療機関を受診することが必要です。なお、高血圧に伴う頭痛の詳細については「朝起きると頭が重いのは高血圧?具体的な症状や原因、対策について解説」をご覧ください。
めまい
高血圧によるめまいは、血圧の急激な変動や脳血流の変化により生じることがあります。特に立ち上がった時にふらつきを感じる起立性低血圧や、血圧が高い状態から急に下がった時に現れやすくなります。また、高血圧により動脈硬化が進行すると、内耳への血流が不安定になり、平衡感覚に影響を与えることもあります。なお、めまいには回転性めまいと浮動性めまいがあり、高血圧に関連するものは主に浮動性で、ふわふわした感じや不安定感として現れます。頻繁にめまいを感じる場合は、血圧管理と併せて耳鼻科的な検査も必要な場合があります。
耳鳴り
高血圧による耳鳴りは、血管内の圧力上昇により内耳の血流が変化することで生じます。特に拍動性耳鳴りと呼ばれる、心臓の鼓動に合わせて「ドクドク」と聞こえるタイプが高血圧患者に多く見られます。これは内耳周辺の血管が拡張し、血流音が聞こえやすくなるためです。また、高血圧により動脈硬化が進行すると、血管の弾力性が失われ、血流の乱流が生じて耳鳴りの原因となることもあります。耳鳴りは日常生活の質を大きく低下させる症状であり、血圧コントロールにより改善することが期待できます。持続する耳鳴りがある場合は、血圧測定と併せて耳鼻科での精査も重要です。なお、高血圧による耳鳴りの詳細については「高血圧患者が注意すべき耳鳴りの症状を解説」をご覧ください。
鼻血
高血圧による鼻血は、鼻腔内の細い血管が高い血圧により破綻することで生じます。特に朝方や血圧が上昇しやすい時間帯に起こりやすく、通常の鼻血よりも止血に時間がかかることがあります。鼻腔内の血管は非常に細く、血圧の上昇に敏感に反応するため、高血圧の症状として現れることがあります。また、高血圧治療薬の中には血液をサラサラにする作用があるものもあり、それにより鼻血が起こりやすくなる場合もあります。
なお、頻繁に鼻血が起こる場合や、止血が困難な場合は、血圧管理の見直しが必要です。また、突然大量の鼻血が出た場合は、緊急受診を検討してください。高血圧による鼻血の詳細については「鼻血が出やすい原因は高血圧?原因や止め方、予防法や注意点を解説」をご覧ください。
赤ら顔
高血圧による赤ら顔は、血管の拡張により皮膚表面の毛細血管が透けて見えることで生じます。特に頬や鼻周辺が赤くなりやすく、血圧が高い状態が続くと慢性的に赤みが残ることがあります。これは血管内の圧力上昇により血管壁に負担がかかり、血管が拡張した状態が続くためです。また、高血圧に伴う交感神経の活性化により、血管収縮と拡張のバランスが崩れることも関与しています。
赤ら顔は美容的な問題として捉えられがちですが、高血圧の早期発見の手がかりとなることもあります。顔の赤みが気になる場合は、血圧測定を行い、必要に応じて医師に相談することをお勧めします。なお、高血圧による赤ら顔の詳細については「赤ら顔の原因と糖尿病・高血圧の関連性 - 医師が解説する症状と対策」をご覧ください。
動悸・息切れ
高血圧による動悸や息切れは、心臓が高い圧力に対抗してポンプ機能を維持しようとするために生じます。血圧が高い状態では、心臓はより強い力で血液を送り出す必要があり、心筋の負担が増加します。その結果、安静時でも心拍数が上昇し、動悸として感じられることがあります。
また軽い運動や階段の昇降でも息切れを感じやすくなります。長期間高血圧が続くと心肥大が進行し、心不全のリスクが高まるため、これらの症状は重要な警告サインです。動悸や息切れが頻繁に起こる場合は、血圧管理と心機能の評価が必要です。
首筋の痛み
高血圧による首筋の痛みは、血管内圧力の上昇により首周辺の血管や筋肉に負担がかかることで生じます。特に後頭部から首の付け根にかけての重苦しい痛みや違和感として現れることが多く、肩こりと混同されることもあります。血圧が上昇すると、頸動脈や椎骨動脈などの主要血管が拡張し、周辺組織に圧迫感を与えます。また、高血圧に伴うストレスや緊張により、首や肩の筋肉が収縮し、痛みが増強することもあります。
首筋の痛みが持続する場合は、血圧測定を行い、必要に応じて医師の診察を受けることが重要です。なお、高血圧による首筋の痛みの詳細については「首筋の痛みの原因は高血圧?症状や対策を解説」をご覧ください。
倦怠感
高血圧による倦怠感は、全身の血管に持続的な負担がかかることで生じる疲労症状です。血圧が高い状態では、心臓や血管系が常に過剰な負荷を受けており、全身のエネルギー消費が増加します。また、高血圧により睡眠の質が低下し、十分な休息が取れないことも倦怠感の原因となります。
さらに、血圧上昇に伴う自律神経の乱れにより、疲労回復が遅れることもあります。慢性的な倦怠感は日常生活の質を大きく低下させるため、血圧管理により改善を図ることが重要です。なお、原因不明の持続的な疲労感がある場合は、血圧測定を含めた健康チェックをお勧めします。
吐き気
高血圧による吐き気は、血圧の急激な上昇や高血圧性脳症により生じることがあります。脳内の血管に過度な圧力がかかると、脳圧が上昇し、嘔吐中枢が刺激されて吐き気や嘔吐が現れます。また、高血圧に伴うめまいや頭痛が強い場合にも、二次的に吐き気を感じることがあります。特に朝方に吐き気を感じることが多く、これは夜間から早朝にかけて血圧が上昇しやすいためです。突然の激しい吐き気や嘔吐は、高血圧緊急症の可能性もあるため、速やかな医療機関受診が必要です。なお、軽度の吐き気でも、血圧が高い状態では注意深い観察が重要です。
高血圧は多くの場合無症状で進行するため、定期的な血圧測定による早期発見が最も重要です。ここで紹介した症状は高血圧に関連する可能性がありますが、これらの症状があるからといって必ずしも高血圧とは限りません。また、症状がないからといって高血圧ではないとも言えません。重要なのは、これらの症状を血圧チェックのきっかけとして捉えることです。特に頭痛、めまい、動悸などの症状が複数組み合わさって現れる場合は、速やかに医療機関を受診し、適切な診断と治療を受けることが大切です。高血圧の早期発見と適切な管理により、重篤な合併症を予防することができます。
なお高血圧の中には、夜間に血圧が十分に下がらない「夜間高血圧」や、診察室では正常でも家庭や職場で高い値を示す「仮面高血圧」と呼ばれるタイプがあります。詳しくは「夜間高血圧とは?症状や原因、睡眠中の血圧上昇リスクと対策を解説」と「仮面高血圧の症状と原因、リスクや治療方法を解説」をご覧ください。
千葉市都賀で高血圧の数値が気になる方へ|正常値と高血圧の基準とは?

血圧は収縮期血圧(上の値)と拡張期血圧(下の値)で表され、日本高血圧学会のガイドラインでは、診察室血圧において正常血圧は120/80mmHg未満、正常高値血圧は120-129/80mmHg未満、Ⅰ度高血圧は130-139/80-89mmHg、Ⅱ度高血圧は140-159/90-99mmHg、Ⅲ度高血圧は160/100mmHg以上と分類されています。重要なのは診察室血圧と家庭血圧では基準値が異なることです。
診察室では医療機関での緊張により血圧が上昇する白衣高血圧現象があるため、家庭血圧の方が基準値として5mmHg程度低く設定されています。一方、家庭血圧では135/85mmHg以上が高血圧と判定され、125/75mmHg未満が正常血圧とされます。なお、現在は家庭血圧による診断がより重視されており、日常生活での血圧管理において家庭での定期測定が推奨されています。
千葉市都賀で高血圧の数値が気になる方へ|危険な数値はいくつから?
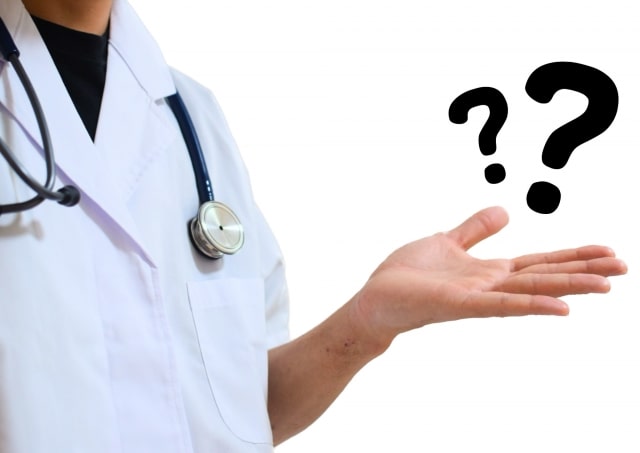
血圧の危険度は段階的に上昇し、診察室血圧140/90mmHg以上で高血圧と診断されます。160/100mmHg以上のⅢ度高血圧では心血管疾患のリスクが著しく高まり、特に180/110mmHg以上では重症高血圧として緊急的な治療が必要となります。そして、収縮期血圧180mmHg以上または拡張期血圧110mmHg以上の状態では、血管壁への負担が極めて大きく、脳出血や急性心筋梗塞、大動脈解離などの致命的な合併症が発生する危険性が急激に増加します。また、このレベルでは高血圧緊急症の可能性もあり、数時間以内に臓器障害が進行する恐れがあります。なお、長期的には140/90mmHg以上の状態が続くことで動脈硬化が進行し、心肥大、慢性腎臓病、脳血管障害のリスクが蓄積されます。血圧が10mmHg上昇するごとに心血管疾患のリスクは約20%増加するため、早期からの適切な血圧管理が重要です。
千葉市都賀で高血圧の数値が気になる方へ|高血圧と関連した症状

高血圧は単独で症状を現すだけでなく、長期間の血圧上昇により全身の臓器に様々な影響を与えます。特に血管が豊富な眼底、脳、腎臓などの臓器では、高血圧による慢性的な負荷により特有の病態が発生することがあります。また、高血圧は他の生活習慣病とも密接に関連しており、複数の疾患が同時に進行することも珍しくありません。ここでは、高血圧と密接に関連する重要な症状や病態について解説します。
手足のしびれ
高血圧による手足のしびれは、血管の動脈硬化により末梢血管の血流が障害されることで生じます。具体的には長期間の高血圧により血管壁が厚くなり、血管内径が狭くなると、手足の先端部分への血液供給が不十分となります。特に指先や足先から始まるしびれや冷感として現れることが多く、進行すると痛みを伴うこともあります。また、高血圧により糖尿病性神経障害が併発している場合は、末梢神経への血流不足によりしびれが増強されます。なお、手足のしびれが持続する場合は、血管の状態を詳しく検査し、血圧管理と併せて血流改善の治療が必要です。早期の対応により症状の進行を防ぐことができます。
高血圧性網膜症
高血圧性網膜症は、眼底の血管が高血圧により障害される病態です。網膜血管は人体で唯一直接観察できる血管であり、高血圧の進行度や全身血管の状態を知る重要な指標となります。例えば、初期段階では血管の細小化や動静脈交叉現象が見られ、進行すると網膜出血、硬性白斑、軟性白斑が現れます。また、重症例では乳頭浮腫や網膜剥離を生じることもあります。なお、患者自身が感じる症状としては、視力低下、視野欠損、飛蚊症などがありますが、初期には自覚症状がないことが多いです。そのため、定期的な眼底検査が大切です。定期的な眼底検査により早期発見が可能であり、血圧管理により進行を抑制できるため、高血圧患者には年1回以上の眼科受診が推奨されます。
高血圧性脳症
高血圧性脳症は、急激な血圧上昇により脳血管の自動調節機能が破綻し、脳浮腫が生じる急性病態です。通常、収縮期血圧が180mmHg以上、拡張期血圧が120mmHg以上の状態で発症リスクが高まります。症状としては激しい頭痛、悪心・嘔吐、意識障害、痙攣、視覚障害などが現れ、放置すると昏睡状態に陥る可能性があります。特に朝方に症状が悪化しやすく、これは血圧の日内変動により早朝に血圧が最も高くなるためです。なお、高血圧性脳症は医学的緊急事態であり、迅速な血圧降下治療が必要ですが、急激すぎる血圧低下は脳梗塞を引き起こす危険性があるため、慎重なコントロールが求められます。詳しくは「高血圧性脳症とは?症状や原因、治療法を解説」をご覧ください。
慢性腎臓病・腎機能低下
高血圧と慢性腎臓病は密接な関係にあります。高血圧は慢性腎臓病の主要な原因であると同時に、腎機能低下により高血圧が悪化するという双方向の関係が存在します。具体的には、長期間の高血圧により腎臓の糸球体や尿細管周囲の血管に動脈硬化が生じ、腎血流量の減少と糸球体濾過量の低下が起こります。そして初期には、微量アルブミン尿として現れ、進行すると蛋白尿、腎機能低下へと発展します。また、腎機能が低下すると体内の水分・塩分調節機能が障害され、血圧がさらに上昇します。さらに、腎臓から分泌されるレニンやエリスロポエチンの分泌異常により、高血圧と貧血が併発することもあります。なお、早期発見のために定期的な尿検査と血清クレアチニン値の測定が重要であり、適切な血圧管理により進行を遅らせることができます。詳しくは「糖尿病性腎症と高血圧の関係性|血圧管理で合併症を防ぐ治療法と対策」をご覧ください。
脂質異常症
高血圧と脂質異常症は互いに影響し合う関係にあり、両者が併存するとメタボリックシンドロームの一部として心血管疾患のリスクが相乗的に増加します。高血圧状態では血管内皮機能が低下し、LDLコレステロールの酸化や血管壁への蓄積が促進されます。また、脂質異常症により動脈硬化が進行すると血管の弾力性が失われ、血圧がさらに上昇するという悪循環が生じます。特に内臓脂肪型肥満がある場合は、インスリン抵抗性により高血圧と脂質異常症の両方が悪化しやすくなります。なお、治療においては血圧管理と脂質管理を同時に行うことが重要であり、生活習慣の改善と併せて、必要に応じて降圧薬とスタチン系薬剤の併用療法が推奨されます。詳しくは「高血圧・糖尿病・高脂血症のトリプルリスク|生活習慣病の重なりが招く危険性と対策」をご覧ください。
千葉市都賀で高血圧の数値が気になる方へ|正しく測るにはどうすればいい?

正確な血圧測定のためには、適切な姿勢と環境の整備が不可欠です。具体的には、背もたれのある椅子に深く腰掛け、両足を床にしっかりとつけて1~2分間安静を保った後に測定を開始してください。そしてカフは上腕に巻き、心臓と同じ高さに保つことが重要です。また、測定タイミングは朝起床後1時間以内が最適で、排尿を済ませ、朝食や薬を服用する前に行ってください。この時間帯は血圧の日内変動を把握する上で最も重要な指標となります。なお、初回は左右両腕で測定し、高い方の値を記録として採用しますが、両腕の差が10mmHg以上ある場合は医師に相談が必要です。また、測定は週に最低3日以上、できれば毎日継続することが推奨されます。さらに、記録は日付、時刻、血圧値、脈拍数を含めて詳細に記載し、体調や生活状況も併記すると診断に有用な情報となります。継続的な記録により血圧の変動パターンが把握でき、適切な治療方針の決定に役立ちます。
千葉市都賀で高血圧の数値が気になる方へ|血圧の数値を下げる方法

高血圧の改善には生活習慣の見直しが基本となります。食事療法、運動療法、ストレス管理を組み合わせることで、薬物療法に頼らずとも血圧の改善が期待できる場合があります。ここでは、効果的な「血圧低下方法」について解説します。ただし、血圧値によっては医師の指導のもとで薬物療法が必要となる場合もあるため、適切な医学的管理と併せて実践することが重要です。
1日6g未満の減塩
減塩は血圧低下において最も重要な食事療法の一つであり、日本高血圧学会では1日の食塩摂取量を6g未満に制限することを推奨しています。具体的には、塩分摂取量を1g減らすだけで収縮期血圧は約1mmHg低下するとされ、継続的な減塩により5~10mmHgの血圧低下効果が期待できます。特に注意すべきは加工食品や外食で、醤油、味噌、漬物、ハム、ソーセージ、インスタント食品などは塩分含有量が高く、これらの摂取量を控えることが効果的です。なお、減塩の実践方法としては、出汁や香辛料、酸味を活用して味付けを工夫し、食品の栄養成分表示を確認する習慣をつけることが大切です。また、カリウムを多く含む野菜や果物の摂取を増やすことで、ナトリウムの排出促進効果も期待できます。
有酸素運動(1日30分ウォーキング)を週3回以上
有酸素運動は血圧低下に非常に効果的であり、定期的な運動により収縮期血圧を4~9mmHg、拡張期血圧を3~5mmHg低下させることができます。推奨される運動は中等度の有酸素運動で、1日30分間のウォーキングを週5回程度継続することが理想的です。また、運動強度は最大心拍数の50~70%程度が適切で、会話ができる程度の負荷で行ってください。なお、運動による血圧低下のメカニズムには、血管内皮機能の改善、自律神経バランスの正常化、体重減少効果などがあります。運動開始直後から血圧低下効果は現れ、継続することで持続的な効果が得られます。ただし、重度の高血圧患者や心疾患を合併している場合は、運動開始前に医師と相談し、適切な運動処方を受けることが重要です。
ストレス管理と睡眠改善
慢性的なストレスと睡眠不足は交感神経を過剰に活性化させ、血圧上昇の重要な原因となります。効果的なストレス管理方法には、深呼吸法、瞑想、ヨガ、リラクゼーション法などがあり、これらを日常的に実践することで副交感神経の活動を促進し、血圧の安定化が期待できます。睡眠に関しては、1日7~8時間の質の良い睡眠を確保することが重要で、睡眠不足や睡眠の質の低下は血圧上昇に直結します。なお、睡眠改善のためには、就寝前のカフェインやアルコールの摂取を控え、規則正しい生活リズムを維持し、寝室環境を整えることが効果的です。また、睡眠時無呼吸症候群がある場合は適切な治療を受けることで、血圧の大幅な改善が期待できます。ストレス管理と良質な睡眠は相互に関連しており、両方を同時に改善することで効果が増大します。
血圧を下げるための生活習慣の改善は、減塩、有酸素運動、ストレス管理と睡眠改善を柱として継続的に実践することが重要です。これらの方法を組み合わせることで10~20mmHgの血圧低下効果が期待でき、軽度から中等度の高血圧では薬物療法を必要としない場合もあります。しかし、収縮期血圧が160mmHg以上または拡張期血圧が100mmHg以上の場合、糖尿病や心疾患などの合併症がある場合、生活習慣改善だけでは目標血圧に到達しない場合には、医師の判断により薬物療法の併用が必要となります。重要なのは、自己判断で治療を中断せず、定期的に医療機関を受診して血圧の経過を監視することです。生活習慣改善と薬物療法は対立するものではなく、相互に補完し合う関係にあるため、医師と相談しながら最適な治療方針を決定することが大切です。
まとめ|高血圧の数値は千葉市都賀の内科で相談できます

高血圧は「サイレントキラー」と呼ばれるように、初期段階では自覚症状がほとんどないまま静かに進行し、気づいた時には心筋梗塞や脳卒中などの重篤な合併症を引き起こすリスクが高まっている恐ろしい疾患です。症状がないからといって安心せず、健康診断で血圧の数値に異常を指摘された場合や、家庭血圧測定で高い値が続く場合は、症状の有無に関わらず早期に医療機関を受診することが重要です。なお、当院では血圧測定から専門的な治療まで、患者一人ひとりの状態に合わせた総合的な医療サービスを提供しています。高血圧の症状に心当たりのある方、もしくは健康診断などで血圧値の異常を指摘された方などいらっしゃいましたら、お気軽にご相談ください。

-
神経内科
神経内科についての記事はこちらをクリック
-
アレルギー内科
アレルギー内科についての記事はこちらをクリック
-
リウマチ内科
リウマチ内科についての記事はこちらをクリック
-
糖尿病・代謝内科
糖尿病・代謝内科についての記事はこちらをクリック
-
各種検診
各種検診についての記事はこちらをクリック
-
内分泌内科
内分泌内科についての記事はこちらをクリック
-
腎臓内科
腎臓内科についての記事はこちらをクリック
-
循環器内科
循環器内科についての記事はこちらをクリック
-
消化器内科
消化器内科についての記事はこちらをクリック
-
呼吸器内科
呼吸器内科についての記事はこちらをクリック
-
内科
内科についての記事はこちらをクリック

- 公費
- ワクチン接種
- 帯状疱疹
- 旅行
- 呼吸器感染症
- 尿路感染症
- 糖代謝
- 健康診断
- 尿糖
- 空腹時血糖値
- 精密検査
- 目標値
- フレイル
- 足が攣る
- 減らす
- 腹囲
- 基準
- メタボ
- 高齢者
- 向き合う
- 家族
- 初診
- 即日
- HbA1c
- 高血圧症
- 数値
- 食後高血糖
- 定期検査
- 伝染性紅斑(りんご病)
- 百日咳
- 仮面高血圧
- 夜間高血圧
- 手足のしびれ
- 管理
- 糖尿病性腎症
- 降圧目標
- 薬物療法
- 高血圧性脳症
- 尿泡
- 目が霞む
- 赤ら顔
- 鼻血が出やすい
- 耳鳴り
- 首の後ろが痛い
- 朝起きると頭が重い
- めまい
- 爪
- 検査方法
- いつから
- インフルエンザ検査
- 空腹
- 痺れる
- かゆい
- 赤い斑点
- 血糖トレンド
- インスリンポンプ
- 脈拍
- 間食
- 入院
- 自宅入院
- 心房細動
- 運動してはいけない
- グリコアルブミン
- スローカロリー
- 血糖自己測定
- フルミスト点鼻液
- 鼻から
- インフルエンザワクチン
- 低血糖
- 大血管症
- がん
- うつ病
- 血糖コントロール
- メタボリックシンドロームとは
- ミトコンドリア糖尿病
- 家族性若年糖尿病
- MODY
- なりやすい
- 日本人
- 何型
- 確率
- 遺伝
- 副鼻腔炎
- 痩せる
- 治らない
- 頭痛
- 血糖値スパイクとは
- いつまで
- コロナ後遺症
- 中耳炎
- インフルエンザ脳症とは
- ワクチン
- 麻疹
- 違い
- D型
- C型
- B型
- A型
- インフルエンザC型
- インフルエンザB型
- インフルエンザA型
- インフルエンザ潜伏期間
- 潜伏期間
- インフルエンザ
- SAS
- 睡眠時無呼吸症候群
- 内科
- ダイアベティス
- 下げる
- 若い女性
- ピーク
- タバコ
- 変異株
- ピロラ
- エリス
- 目
- 食後
- 吐き気
- 60代
- 不眠
- 血糖値スパイク
- カフェイン
- 30代
- うつ
- 50代
- 40代
- 更年期
- 相談
- 方法
- タイプ
- 関連
- 20代
- 診察
- 評価法
- 診断基準
- 関係性
- 女性ホルモン
- 女性
- 副作用
- 費用
- デメリット
- メリット
- 減感作療法
- 男性
- チェック
- 不眠症
- 居眠り
- 意識が朦朧
- 眠気
- 痒み
- 皮膚
- 病名変更
- 名称変更
- 塩分
- 病気
- 脱毛症
- 糖質
- 抜け毛
- バナナ
- 摂取量
- コーヒー
- 糖尿病性ED
- ED
- 偏見
- 例
- 病名
- 言葉
- アドボカシー活動
- スティグマ
- ホルモン
- 精神疾患
- ストレス
- 糖尿病網膜症
- 糖尿病ケトアシドーシス
- 影響
- 喫煙
- 経口血糖降下薬
- 糖尿病かもしれない
- 境界型糖尿病
- 糖尿病予備群
- インスリン療法
- 骨折
- 骨粗鬆症
- 心筋梗塞
- 後遺症
- 脳梗塞
- 1型糖尿病
- 検診
- 生活習慣
- 歯周病
- 重症化
- 新型コロナウイルス
- 敗血症性ショック
- 感染症
- 敗血症
- 水分補給
- 関係
- 脱水症状
- 注意
- 効果
- 糖尿病予防
- 糖質制限
- 食べ物
- アルコール
- お酒
- 妊娠糖尿病
- 初期症状
- 慢性合併症
- 糖尿病腎症
- 理由
- スキンケア
- 保湿剤
- 痒さ
- 血糖値
- 食事
- 食べてはいけないもの
- 乳製品
- おすすめ
- 食生活
- ヒトヘルペスウイルス
- ウイルス
- 発熱
- 突発性発疹
- 呼吸器
- ヒトメタニューモウイルス感染症
- ヒトメタニューモウイルス
- 感染経路
- 小児
- RSウイルス感染症
- 手足口病
- 特徴
- 夏風邪
- ヘルパンギーナ
- 糖尿病足病変
- 血糖
- 糖尿病チェック
- 足
- 1型糖尿病
- 2型糖尿病
- 合併症
- インスリン
- 運動療法
- 子供
- くしゃみ
- 新型コロナウイルス感染症
- 点眼薬
- 点鼻薬
- 内服薬
- 有効
- 薬
- 対策
- 飛散
- 舌下免疫療法
- アナフィラキシーショック
- アレルギー
- 治療法
- 花粉症
- 無症状
- 待機期間
- 濃厚接触
- 期間
- 甲状腺ホルモン
- 甲状腺機能低下症
- 風邪
- 初期
- 感染対策
- オミクロン株
- 接種券
- 対象
- 新型コロナワクチン
- 3回目
- 甲状腺
- 栄養素
- 糖尿病
- 血圧
- 減塩
- 動脈硬化
- 食事療法
- 生活習慣病
- DASH食
- 高血圧
- 若葉区
- 脂質異常症
- 都賀
- 高脂血症
- 感染
- 運動
- 飲酒
- 接種後
- 接種率
- 千葉市
- 副反応
- 種類
- 接種
- 予約
- コロナワクチン
- コロナ
- 診断
- 予防
- 治療
- 改善
- 原因
- 検査
- 症状


 クリニック紹介
クリニック紹介
 診療のご案内
診療のご案内

